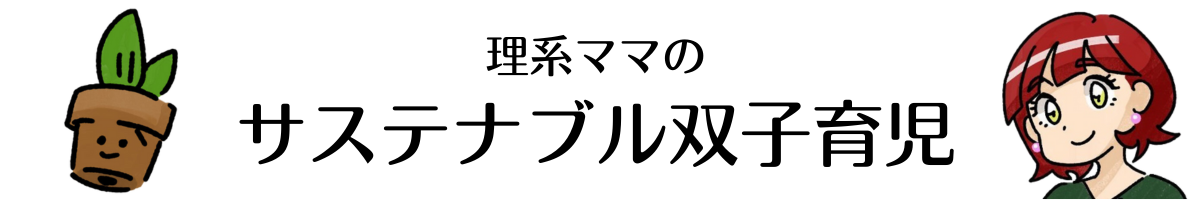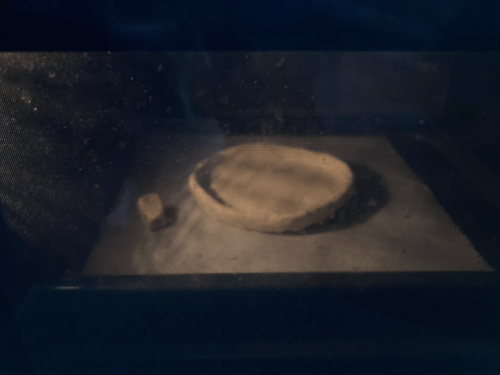6月は梅が旬。
梅雨の字に梅が入っているのは、
梅の実が熟す時期だからという説もあります。
その梅を使って、
梅干しや梅酒などの保存食を作る
日本ならではの手仕事を「梅仕事」といいます。
年に1度梅仕事をしておけば、
その後も長く梅を楽しむことができるので、
梅好きの方には嬉しい季節。
そんな梅仕事の中から、今回は
梅シロップ作りに初挑戦。
シロップの下準備の様子を記録しました。
[char no=”1″ char=”hazeran”]どんなふうに仕上がるのかとっても楽しみだわ。[/char]
[char no=”5″ char=”はっちー”]それではいってみよう![/char]
はじめての梅仕事は梅シロップ作り
入梅(6/11ごろ)を過ぎ、
今か今かと青梅が売られるのを
楽しみにしていました。
実はずっとやってみたかった梅仕事。
夫が梅を好んで食べないため、
大量に作っても食べきれるか心配なこともあり、
なかなかできていませんでした。
今年は実家に里帰りしていて、
母も妹たちもみんな梅が大好きなので、
これはチャンス!と思い挑戦してみることに。
夏真っ盛りの8月ごろに飲むのを目標に
仕込んでいきます。
2-1 梅シロップ作りに使った材料
梅シロップ作りの材料
・青梅1kg
・氷砂糖1kg
・食酢200ml
発酵予防のために食酢を入れました。
お酢を入れると完成した時に酸っぱくなるのかな?
そういえば、
「氷砂糖」を使う機会って私はなかなかなくて、
梅仕事をするまで、
カンパンに入っているものしか
出会ったことがなかったです^^;
氷砂糖はゆっくり溶けるので、
はじめは外にある水分が梅の方に移動していき、
氷砂糖が溶けて梅の外にある糖の濃度が上がり始めると
梅の水分に溶けた風味を
じわじわと引き出していくんだそう。
[char no=”1″ char=”hazeran”]浸透圧の差をつかった知恵ね。[/char]
[char no=”5″ char=”はっちー”]代わりに砂糖を使うと
梅の水分がすぐに抜けるから、
梅がすぐにしわしわになるんだって。[/char]
[char no=”1″ char=”hazeran”]短い期間でシロップにしたかったら
お砂糖でもいいかもね。[/char]
※氷砂糖を使う理由については下記サイトを参照しました。
2-2 青梅のヘタ取り

買ってきたのは1キロの青梅。
まずは洗う前にヘタを取っていきます。
作業をしながら
爽やかな梅の香りに思わず頬が緩みます。
シロップが完成したら、ソーダで割ろうかな、
ゼリーにしようかな、なんて
色々考えていたらあっという間にヘタとりが終わりました。
2-3 梅を洗ったらふいて、乾燥

ヘタが取れたら、梅を洗います。
保存容器の中に水が入ってしまうと
痛む原因になるので、
1つ1つ丁寧にふいていきます。
その後ザルに入れて、
1時間ほど乾燥させました。
2-4 梅と氷砂糖交互に入れる
洗った梅の水気が取れたら、
保存容器の中に梅と氷砂糖を交互に入れていきます。
梅と氷砂糖は1/3ずつくらいを目安に
交互に入れていくと綺麗な層になりました。

写真は1日が経過した様子。
楽しみすぎて、
お腹が空くたびに保存容器をひっくり返しています。
[char no=”1″ char=”hazeran”]まだかなー、まだかなー。[/char]
[char no=”5″ char=”はっちー”]夏が来るのが待ち遠しいね。[/char]
これから毎日上下を逆さにしたりして
中身を揺すりながら、
様子を見ていきたいと思います。
少しずつ変化してきたら写真を更新予定。
今回は青梅にしましたが、
梅の熟し具合よって風味も変わるそう。
6月中旬に取れる少し熟した梅は
より芳醇な香りがするみたい。
下旬のよく熟した梅で
梅干しも作ってみたいですね。
梅一つとってもいろいろな梅仕事が楽しめるので、
毎年の梅雨が楽しみになるきっかけができて
とってもうれしいです^^
季節の手仕事で、何でもない1日を楽しい1日にできる
梅仕事を通して、
旬の食材の香りを楽しめただけでなく、
家族と笑顔で会話をすることができました。
季節に合わせた日本ならではの食や習慣は、
何でもない1日を
とても充実したものにしてくれますね。
これからも、季節感を大切にしながら
日々を楽しみたいと思います♪
[char no=”1″ char=”hazeran”]ここまで読んでくれて、どうもありがとう![/char]